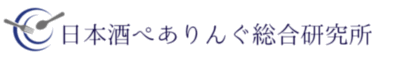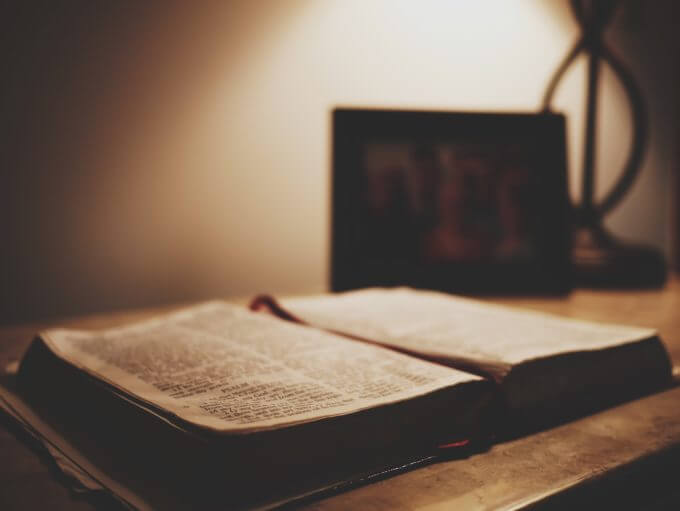最近「食中酒」という言葉をよく聞きますが、実はその歴史はまだ浅いというお話を。
日本の食文化に「マリアージュ」の概念はない
意外に思われる方も多いでしょうが、旧来の日本酒と食事の間にはフレンチでいうところの「マリアージュ」や「ペアリング」の考えはありません。
基本的に食事は食事、酒は酒、それぞれが別個のプロダクトとして存在していたのです。食事中に日本酒を飲むことも当然ありますが、その場合でも日本酒には料理の邪魔をしないことが求められ、あえて与えられる役割があるならば、お茶のように一旦口中をすっきりさせてリセットさせることくらいでした。
「菜」と「肴」
日本の食文化には「菜」と「肴」の考え方があります。
「菜」は「な」と読みますが、日常の食事における「おかず」のことで、米飯(主食)と共に食されることを想定された副食のことを表します。上でも書いたように、米飯とおかずの関係性に酒が割って入ることはなく、食事と酒はまた別物として並列に存在していました。言い換えれば、食事に酒を合わせて楽しむ考えそのものがなかったんですね。
日本酒の起源をたどると、もともとは神事や祭祀で酔うためのツールでした。「酔う」とはつまり非日常であり、その状態になることで神とのコンタクトをはかったのです。そのため、酒は単体で飲用されることがほとんどでした。
そこから儀礼や公的な礼講でも飲用されるようになり、宴席において欠かせないものとなっていきます。宴席なので、当然酒と一緒にいろいろな料理は提供されたようですが、ここでの料理が「肴」にあたります。もともとは「酒」のおかずである「菜」で「酒菜」と書いたようですが、それがいつしか転じて「肴」と表記するようになったようです。
肴は酒ありきの考え方で、酒を美味しくたくさん飲むための食べ物を指します。ここでも「酒は酔うために飲むもの」という立ち位置は変わっておらず、あくまでも主体は料理ではなく酒でした。
実際のところ「菜」も「肴」も中身は同じようなものであったと考えられます。その料理とペアになるのが米飯だと「菜」になり、酒だと「肴」になるんですね。
日本酒のペアリングの元祖はこの「肴」からと言っていいとは思いますが、ただ、肴は酒の引き立て役で、添え物でしかないわけです。少なくとも食事と合わせて新しい味わいを生み出す西欧的なマリアージュの概念からは遠いものと言えます。
さらに時代が進むと、当然のように酒も一般化して日常で消費されるようになりますが、相変わらず「菜」と交わることはなく、酒は酒、食事は食事として互いの領域を侵すことなく平行線をたどったまま食文化が醸成されていきました。現在でも夕飯と晩酌は別であることをイメージすると理解しやすいのではないでしょうか。
西欧の考え方
ワインやビールと日本酒が根本的に異なるのはここです。ワインやビールは原則それ自体を主体としては考えられていません。必ずといっていいほど、どんな食べ物と一緒に飲むかを考えます。つまり飲み物も食事の一部であることを意識して設計されているのです。
(最近流行りのワインバーなどでは「肴」的になっているというか、あるワインを楽しむためにどんなつまみを合わせるかを考えるようになってきているのは面白いところです。)
食中酒の概念の浸透
近年になってワインやビールが市民権を獲得し、日本の食卓を彩るようになります。それにともなって、こうした西欧的なマリアージュや食中酒といった概念もあわせて一般に浸透していきました。恐らく90年代に入ってからでしょうか。
このあたりで、ようやく日本酒にも西欧的な食中酒の考え方が適用されるようになってきたと思われます。
ですから、日本酒そのものは歴史が長いんですが、食事と一体化したペアリングやマリアージュの概念はまだ始まったばかりなんですね。
ちなみに、フレンチで一皿ごとに違うワインを合わせる「提供スタイルとしてのペアリング」が流行し始めたのはここ数年のことです。この点において日本酒に至ってはまだごく一部でしか認知されておらず、これからどんどん広まっていくことを期待しています。
まとめ
これからの時代は日本酒でも多様な楽しみ方が求められます。もちろん単体で素晴らしい酒を飲むのもいいんですが、さらに視野を広げていくには、いかに食事とペアリングさせて新しい楽しみ方を創出していけるかが重要なんじゃないでしょうか。
それではまた。
参考文献:
『「飲食」というレッスン―フランスと日本の食卓から』福田 育弘(著) 三修社 刊
『HUMAN vol.5: 知の森へのいざない』人間文化研究機構(監修) 平凡社 刊